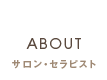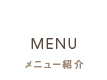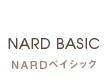アロマで肝臓に負担がかかる?
アロマセラピストが気をつけていること
アロマを楽しむうえで気をつけたいこと。
細かいことも含めれば、本当にたくさんあるのですが、
その中でも、セラピスト故に私自身が意識的に気をつけていることがあります。
それは…精油を使わない日を作ること、です。
精油の「代謝経路」
芳香浴や吸入法、トリートメントなどを行うことで、精油の成分は呼吸器や皮膚から、体に吸収されていきます。
その後毛細血管に取り込まれ、血流にのって全身を巡ります。
そして各器官に働きかけたのち、肝臓や腎臓で解毒、代謝され、尿や汗などで体の外へ出ていきます。
これが、精油の「代謝経路(たいしゃけいろ)」と呼ばれているものです。
どんなに好きな香りだとしても
どんなにその人の体に必要な精油だったとしても。
アルコールやお薬同様、精油の化学成分も代謝され、きちんと排出される必要があります。
精油は体にとって異物であるということ
精油は植物の成分がギュギュっと濃縮されたもの。
以前、別の記事でも書きましたが、例えばローズ精油だと1滴でバラ約120本分に相当します。
それだけ高濃度な物体であることを忘れてはいけません。
精油とは芳香成分の化合物。体にとっては異物です。
体にどんどん蓄積されていいものではありません。
排泄は吸収と同じくらい大切
ですから、トリートメントを受けていただいたときは、いつも水分を多めに摂るようにお伝えしています。
排尿を促したり、血流を悪くしないためにも体を温めるようにしたり。
排出を意識して行動することが大切です。
アロマを長く楽しむために気をつけましょう
ご自宅で芳香浴を楽しむときも同様で、のべつ幕なしに、毎日まいにちずーっと同じ香りを嗅ぎ続けるのは良くありません。
部屋の広さに応じて芳香浴中でも換気したり、日によって違う精油にしてみたり。
そういう対策をしていても、やっぱり連日使用し続けることは肝臓腎臓への負担が気になります。
ということで、精油を使わない日、いわゆる休肝日を作ることをおすすめします。
たまには自然の中を散歩して、濃縮ではないストレートな植物の香りを楽しんでみるのも良いですね。
私もずっと精油ばかり触っていると、焼きたてパンの匂いやお出汁の香り、とり込んだばかりの洗濯物の匂いなど、生活臭(っていうのかしら?)が恋しくなって、嗅ぐとほっと安心する…ということがあります。
それだけ、大きな力を持っている精油。
気をつけるべきことを気をつけて、長く楽しみましょう。
maco